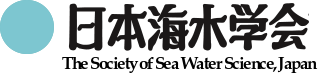日本海水学会の会長を拝命いたしました東京農工大学の滝山です。伝統ある学会の運営に携わることとなり、身の引き締まる思いとともに、新たな歩みを進める覚悟を新たにしております。これまで本学会を支えてこられた歴代の会長や役員の先生方、そして会員の皆様に心より御礼申し上げます。
本学会は「海水」を共通の基盤とし、製塩技術や海水を資源として利用する技術から、海水と地球環境の相互作用、生物と海水の関わりまで、専門の分野を越えて交流し議論を深めることが、大きな特徴であり強みです。これを支える一つが「電気透析および膜技術研究会」「海水環境構造物腐食防食研究会」「環境・生物資源研究会」「塩と食の研究会」「分析科学研究会」「海水資源・環境研究会」という6つの研究会であり、それぞれが多様な課題に取り組んでいます。
学会誌については、和文誌「日本海水学会誌」と英文誌「Salt and Seawater Science & Technology(SSST)」の二誌が本学会の学術発信の要です。これらはすでに多くの研究者・技術者の皆様のご努力によって充実してきており、総説・解説・原著論文の質をさらに高めていくことが望まれます。特に、SSSTでは、多様な分野の研究成果を積極的に取り込みながら、国際的評価の向上に努めてまいります。
また、本学会が産学連携の側面を持っていることは、大きな誇りです。大学や国公立機関の研究者だけでなく、多くの企業研究者が参加し、知見と技術を共有してきました。今後は企業とアカデミアとの対話をさらに促進し、特に学生・若手研究者が企業研究者と接する機会を増やすことで、人材育成と実践的な応用研究の両立を図っていきたいと考えております。さらに、技術や知識の継承もまた本学会の重要な使命であります。若手会の活発な活動を支援しながら、経験豊かな先輩方の知識や技能を着実に次世代へと伝えてまいります。
未来を見据えるとき、海水に係わる課題は多岐にわたります。製塩技術のさらなる深化、資源活用の持続可能性、海洋環境の保全、さらには気候変動との結びつきなど、解決すべきテーマは尽きません。本学会が持つ学際性、多様な研究会、豊かな交流の場を活かし、これらの課題に総合的に取り組んでいきたいと考えております。
会員の皆様のお力添えとご協力なくして、いかなる目標も達成し得ません。これからの学会活動に、これまで以上に積極的に関わっていただき、知と技術の創出、そして共有の輪をともに広げてまいりましょう。皆様とともに日本海水学会をより活気ある、開かれた、そして未来につながる学会として築いていけることを心より願っております。
令和7年7月吉日
日本海水学会 会長 滝山 博志